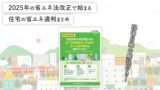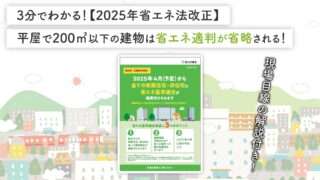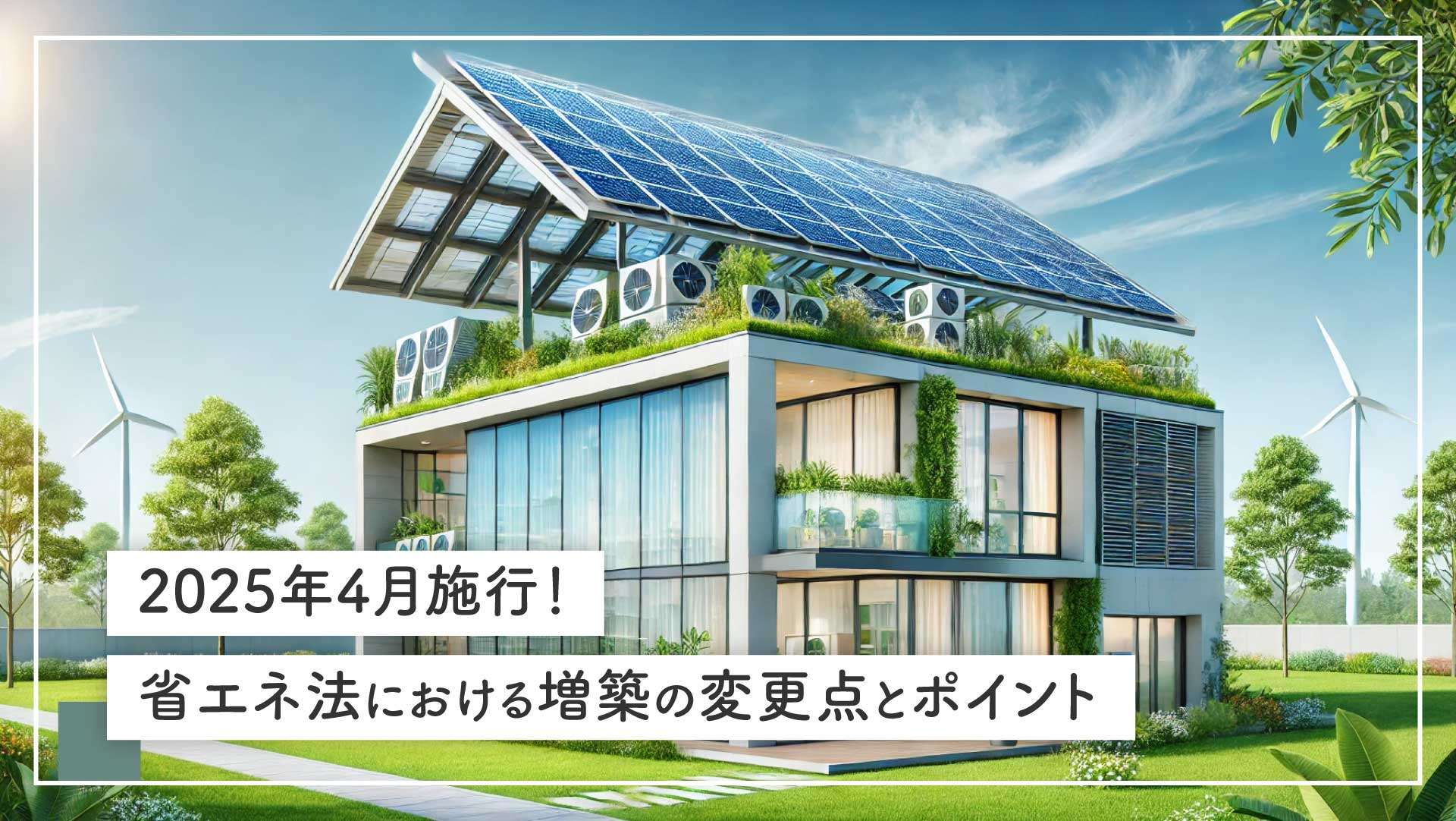2025年4月から「建築物省エネ法」が改正され、建築確認や省エネ適判の手続きが大きく変わります。
この改正は、建築物の省エネ性能を向上させるだけでなく、審査手続きをより合理化し、スムーズに進めることを目的としています。
しかし、改正された法律の内容は専門的で難解なため、「何が変わるのか?」「確認申請の流れはどうなるのか?」と疑問を持つ人も多いでしょう。
そこで本記事では、2025年4月からの改正省エネ法のポイントを初心者にもわかりやすく解説します。
また、建築確認申請や省エネ計算の流れを具体的に説明し、設計者や建築関係者がスムーズに対応できるようにサポートします。
「省エネ法の改正で、確認申請がスムーズに通らなくなるのでは?」と不安に思っている方も、 本記事を読めば、どのように手続きすればよいのかが明確になるはずです。
それでは、改正省エネ法の具体的な変更点から見ていきましょう!
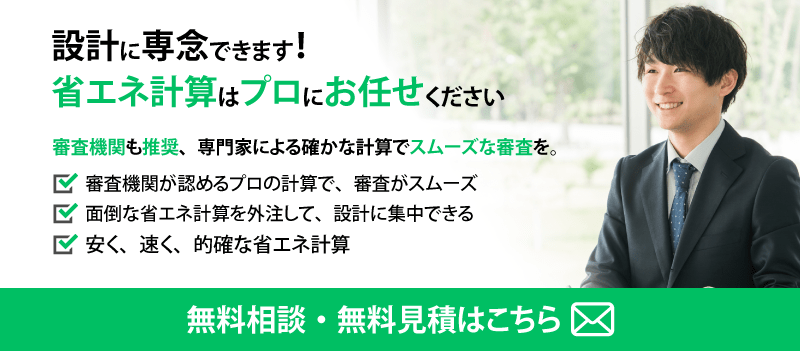
何が変わる?改正省エネ法のポイント
2025年4月の改正により、省エネ適判や確認申請の手続きにいくつかの重要な変更が加えられます。
ここでは、その主なポイントを紹介します。
増改築に関する法改正はこちらをご覧ください
省エネ適判の省略できる仕組みの新設
これまで、300㎡以上の非住宅では省エネ適判(省エネ基準適合判定)を受ける必要がありました。
それが2025年の法改正によって確認申請が伴う、住宅も含めた全ての規模の建物で省エネ基準への適合が義務付けられることになりました。
省エネ法の詳しい解説についてはこちらをご覧ください。
省エネ基準への適合は義務付けられましたが、審査の手続きを合理化する目的で省エネ適判の審査を省略する仕組みも合わせて設けられました。
今回、政府が発表した内容では「設計住宅性能評価書」や 「長期優良住宅」 を取得することで、省エネ適判を省略できるようになります。
省略の条件
- 設計住宅性能評価書の取得
- 確認審査の末日3日前までに評価書を建築主事に提出
- 共同住宅の場合は全住戸の評価書が必要
この制度により、省エネ適判の負担が軽減され、手続きを迅速に進めることが可能になります。
ただし、これはあくまでも審査の省略のみであり、完了検査時に省エネの検査は行われますので、次の章で解説する変更申請の出し忘れやそれに係る時間と費用にも注意して進めていきましょう。
また、平屋で200㎡未満の建物や仕様基準を用いて設計された建物についても省エネ適判の審査は省略されます。
こちらの詳しい説明は下記の記事をご覧ください。
建築確認と省エネ適判の連携
新しいルールでは、建築確認申請時に「宣言書」の提出が必要になります。
これは、評価書の提出が期限までに可能であることを申請者が約束する書類です。
もし期限までに評価書を提出できない場合は、通常通り省エネ適判を受ける必要があります。
そのため、申請のタイミングをしっかりと調整することが重要です。
計画変更時の手続き
建築確認を受けた後に計画を変更する場合、変更の種類に応じて省エネ計算の書類も変更の手続きが必要になります。
省エネ性能がどのように変化したかによって、以下のルートに分かれ申請方法が異なります。
- ルートA(省エネ性能が向上 or 影響なし) → 軽微な変更説明書を提出
- ルートB(一定範囲で省エネ性能が低下) → 変更設計住宅性能評価書の提出
- その他の変更 → 新規の省エネ適判が必要
特に、省エネ適判の省略を前提とした場合、後からの変更が制限される 可能性があるため、慎重に計画を進める必要があります。
具体的な申請の流れ
改正後の省エネ法に基づく建築確認申請の流れは以下のようになります。
- ステップ1建築確認申請の提出
まず、建築主事や指定確認検査機関に対し、建築確認申請を行います。
この際、省エネ適判が必要かどうかを判断し、該当する場合は適切な書類を準備します。 - ステップ2設計住宅性能評価の取得(必要な場合)
省エネ適判を省略したい場合は、設計住宅性能評価書を取得し、確認審査の3日前までに提出する必要があります。
- ステップ3確認済証の交付
建築確認申請が適正であると判断された場合、確認済証が交付されます。
- ステップ4建築工事の実施
確認済証が交付された後、建築工事を進めることができます。
- ステップ5完了検査の申請と審査
建築工事が完了したら、完了検査を申請し、省エネ性能を含む適合性を確認してもらいます。
- ステップ6検査済証の交付
完了検査に合格すると、検査済証が交付され、建築物の使用が可能になります。
この流れをしっかりと理解し、スムーズな手続きができるように準備しておきましょう。
これからの建築確認と省エネ計算で気をつけること
設計住宅性能評価書の早期取得
省エネ適判を省略するためには、確認審査の末日3日前までに評価書を建築主事に提出するためにも、設計住宅性能評価書をスムーズに取得することが重要です。
省エネ適判が必要なケースの見極め
全ての建築物が省エネ適判を省略できるわけではありません。
2,000㎡以上の非住宅などは昨年に省エネ基準が厳しくなり、建物の用途によってはクリアが難しくなっています。
どんな用途・規模の建物をいつまでに建てなければいけないか、それにはどんな申請が必要でどれくらいの時間がかかるかについてはしっかりと押さえて計画を進めるようにしていきましょう。
解説記事はこちら
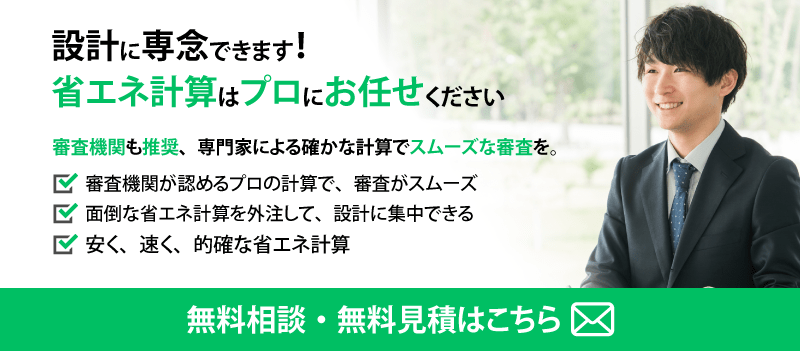
変更時の対応
計画変更が発生した場合、変更申請を受ける必要があるかどうかを確認しましょう。
機器を変更した結果、計算結果がどうなるかがルートを左右しますので、基準値ギリギリでクリアしている建物は、機器変更の都度、計算書に反映して基準を超えてしまっていないか確認しながら進めた方が良いです。
省エネ計算の変更申請が必要になるのはあくまでも省エネ計算で使用した設備が変更になった時なので、計算で使用していない機器の変更は対象外となります。
省エネ計算で使用する設備の設備はこちらの記事で解説をしています。
期限管理の徹底
確認申請の期限や評価書の提出期限を守ることが、スムーズな手続きのカギとなります。
また、審査機関がスムーズに審査を行うためにも、省エネ計算の代行会社の利用を審査機関側も推奨しています。
もし、ご自身で勉強しながら計算を始めようとされているのであれば、時間的余裕をたっぷりと持って進められることをお勧めします。
これから省エネ計算の専門会社も忙しくなっていきますので、「計算を忘れていた」「計算したけど質疑が終わらない」だから急いでやって欲しいと言っても限界があります。
少しでもお得に、安心して進められる省エネ計算の会社を早めに見つけておかれることを私からもお勧めいたします。
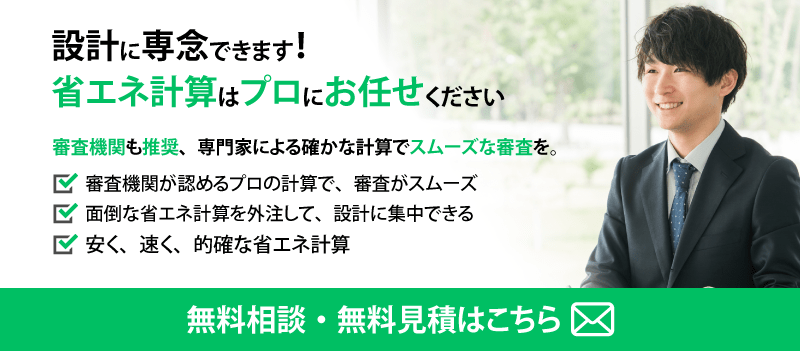
まとめ
改正省エネ法により、建築確認や省エネ適判の手続きが大きく変わりました。
- 設計住宅性能評価書を取得すれば、省エネ適判の省略が可能。
- 申請のタイミングや手続きを正しく理解し、スムーズに対応することが重要。
- 計画変更時の対応や期限管理にも注意が必要。
新しい制度に適応することで、建築確認手続きをより円滑に進めることができます。
今後の建築計画に役立ててください!